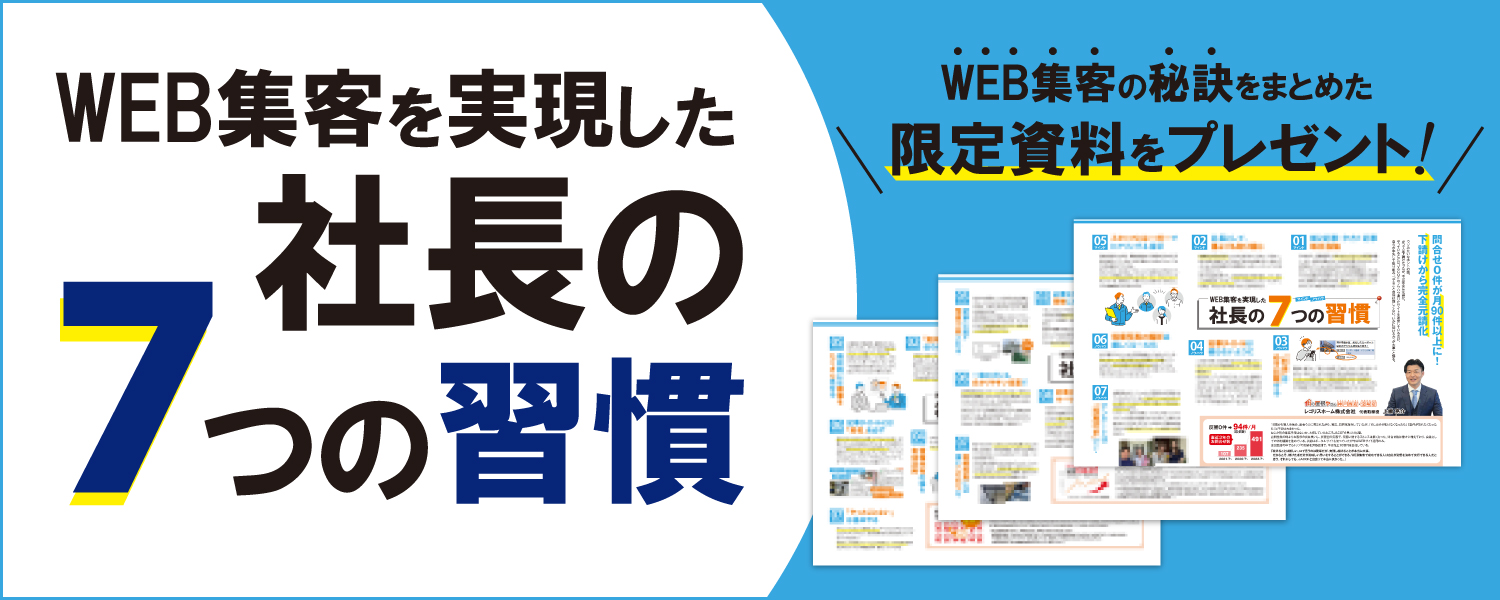- Webコンサルブログ
- 会社の生存率をWebサイトで上げる方法|経営安定と顧客獲得を両立する持続的成長の仕組み
会社の生存率をWebサイトで上げる方法|経営安定と顧客獲得を両立する持続的成長の仕組み
会社の生存率は、なぜここまで低いのか
日本政策金融公庫の調査によると、創業から10年後も存続している会社は全体の約6.3%しかありません。
この数字を見て、「うちは大丈夫だろう」と思う経営者ほど危険です。なぜなら、倒産とは「資金ショート」だけで起きるものではないからです。
多くの企業が静かに衰退していく原因は、顧客との関係性が途切れること。
売上の減少は、集客や営業の問題ではなく、“選ばれなくなった”構造的なサインなのです。
この数字を見て、「うちは大丈夫だろう」と思う経営者ほど危険です。なぜなら、倒産とは「資金ショート」だけで起きるものではないからです。
多くの企業が静かに衰退していく原因は、顧客との関係性が途切れること。
売上の減少は、集客や営業の問題ではなく、“選ばれなくなった”構造的なサインなのです。
「倒産しない」ではなく「選ばれ続ける」
多くの経営者が「生存率を上げる=倒産を防ぐ」と考えます。
しかし実際には、“顧客から選ばれ続ける会社”が結果として倒産しないのです。
つまり、資金繰りや経費削減といった守りの経営だけでなく、
「どうすれば地域で・業界で・顧客にとって“なくてはならない存在”になれるか」
という攻めの仕組み作りが必要です。
その要となるのが、Web集客の再構築です。
ホームページやブログ、SNSなどのデジタル接点を「単なる宣伝」から「顧客接点の自動化装置」へ変えることで、
生存率は大きく改善します。
しかし実際には、“顧客から選ばれ続ける会社”が結果として倒産しないのです。
つまり、資金繰りや経費削減といった守りの経営だけでなく、
「どうすれば地域で・業界で・顧客にとって“なくてはならない存在”になれるか」
という攻めの仕組み作りが必要です。
その要となるのが、Web集客の再構築です。
ホームページやブログ、SNSなどのデジタル接点を「単なる宣伝」から「顧客接点の自動化装置」へ変えることで、
生存率は大きく改善します。
生存率=「再来率 × 信頼度 × 露出量」
ここで、少し数式で考えてみましょう。
多くの会社が「売上=客数×単価」でしか考えていませんが、
会社の生存率は次のような式で表せます。
生存率 = 再来率 × 信頼度 × 露出量
・再来率:一度関わったお客様が再び相談してくれる確率
・信頼度:紹介や口コミにつながる満足度
・露出量:認知される機会の数(=Web上で見つけてもらえる頻度)
この3つのどれかが欠けると、
時間とともに会社の存在が薄れ、選ばれなくなります。
例えば、リフォーム会社の場合。
「施工技術」だけで信頼を得ても、発信を止めれば露出量が減ります。
また、広告を打っても、再来率が低ければ一過性です。
つまり、“生存率を上げる”とはこの3要素をバランスよく高め続ける経営を意味します。
多くの会社が「売上=客数×単価」でしか考えていませんが、
会社の生存率は次のような式で表せます。
生存率 = 再来率 × 信頼度 × 露出量
・再来率:一度関わったお客様が再び相談してくれる確率
・信頼度:紹介や口コミにつながる満足度
・露出量:認知される機会の数(=Web上で見つけてもらえる頻度)
この3つのどれかが欠けると、
時間とともに会社の存在が薄れ、選ばれなくなります。
例えば、リフォーム会社の場合。
「施工技術」だけで信頼を得ても、発信を止めれば露出量が減ります。
また、広告を打っても、再来率が低ければ一過性です。
つまり、“生存率を上げる”とはこの3要素をバランスよく高め続ける経営を意味します。
実務ノウハウ①:Web集客の目的を「見つけてもらう」から「選ばれる」に変える
多くの会社が「検索で上位表示されたい」と言います。
しかし、それはあくまで見つけてもらうための第一歩です。
生存率を上げるためには、見つけられた後に信頼される情報発信が必要です。
〇施工事例:単なる写真ではなく、「なぜこの工法を選んだのか」を説明する
〇スタッフ紹介:資格・経験だけでなく、「どんな想いで仕事をしているか」を語る
〇ブログ記事:季節の話題や地域性を織り交ぜて、“顔が見える発信”をする
これらを積み重ねることで、Web上に「信頼資産」が蓄積されます。
それが、将来的に再来率と信頼度を押し上げる最大の要因になります。
しかし、それはあくまで見つけてもらうための第一歩です。
生存率を上げるためには、見つけられた後に信頼される情報発信が必要です。
〇施工事例:単なる写真ではなく、「なぜこの工法を選んだのか」を説明する
〇スタッフ紹介:資格・経験だけでなく、「どんな想いで仕事をしているか」を語る
〇ブログ記事:季節の話題や地域性を織り交ぜて、“顔が見える発信”をする
これらを積み重ねることで、Web上に「信頼資産」が蓄積されます。
それが、将来的に再来率と信頼度を押し上げる最大の要因になります。
実務ノウハウ②:問い合わせ導線は「数」より「深さ」を意識する
会社のWebサイトを見ると、「とにかく問い合わせボタンを増やす」ケースが多いです。
しかし、ユーザーはそれでは動きません。
むしろ、「自分の悩みに寄り添ってくれる導線」を用意することが重要です。
例えば、以下のような工夫が有効です。
〇「屋根の劣化チェック」「無料点検シミュレーション」など、参加型のCTAを設置
〇施工事例ページ内に「同じ悩みを持つ方はこちら」導線を設置
〇問い合わせ後のフォロー体制(自動返信メールやLINE)を整える
問い合わせ数を“深さ”で捉える発想が、結果的に生存率を上げます。
しかし、ユーザーはそれでは動きません。
むしろ、「自分の悩みに寄り添ってくれる導線」を用意することが重要です。
例えば、以下のような工夫が有効です。
〇「屋根の劣化チェック」「無料点検シミュレーション」など、参加型のCTAを設置
〇施工事例ページ内に「同じ悩みを持つ方はこちら」導線を設置
〇問い合わせ後のフォロー体制(自動返信メールやLINE)を整える
問い合わせ数を“深さ”で捉える発想が、結果的に生存率を上げます。
実務ノウハウ③:データ計測を「集客」だけで終わらせない
Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て、
「アクセスが増えた」「減った」で終わっていませんか?
それだけでは、生存率は上がりません。
アクセスの質=見込み客との関係性を測ることが大切です。
・どのページを読んだ人が問い合わせしたのか
・どんな地域からの流入が成約につながったのか
・一度見た人が何日後に再訪したのか
これらを把握することで、
「顧客が選ぶ理由」をデータで再現できるようになります。
そして、それをWebや営業トークに反映することで、
経営全体の精度が上がります。
「アクセスが増えた」「減った」で終わっていませんか?
それだけでは、生存率は上がりません。
アクセスの質=見込み客との関係性を測ることが大切です。
・どのページを読んだ人が問い合わせしたのか
・どんな地域からの流入が成約につながったのか
・一度見た人が何日後に再訪したのか
これらを把握することで、
「顧客が選ぶ理由」をデータで再現できるようになります。
そして、それをWebや営業トークに反映することで、
経営全体の精度が上がります。
Web発信は“経営の生命維持装置”
SNSや広告は短期的な集客ツールに見えますが、
正しく設計すれば“生存率を高める生命維持装置”になります。
・ブログ:検索経由での新規顧客との接点をつくる
・施工事例:再来率・紹介率を上げるストックコンテンツ
・LINE・メール:信頼関係を維持するリピート導線
この3層を連携させることで、
“Webが自動で顧客との関係を維持してくれる状態”が作れます。
正しく設計すれば“生存率を高める生命維持装置”になります。
・ブログ:検索経由での新規顧客との接点をつくる
・施工事例:再来率・紹介率を上げるストックコンテンツ
・LINE・メール:信頼関係を維持するリピート導線
この3層を連携させることで、
“Webが自動で顧客との関係を維持してくれる状態”が作れます。
生存率を上げる会社は、売上より「信頼残高」を増やしている
経営とは、売上を追うことではなく信頼残高を積み上げることです。
その信頼が、次の紹介・再来・契約につながり、結果として会社の寿命を延ばします。
つまり、生存率を上げたいなら、
「信頼を蓄積し続ける仕組み」を今すぐ作ることです。
Webサイト、SNS、口コミ、すべての接点が“信頼を積む場所”になるように設計しましょう。
その信頼が、次の紹介・再来・契約につながり、結果として会社の寿命を延ばします。
つまり、生存率を上げたいなら、
「信頼を蓄積し続ける仕組み」を今すぐ作ることです。
Webサイト、SNS、口コミ、すべての接点が“信頼を積む場所”になるように設計しましょう。