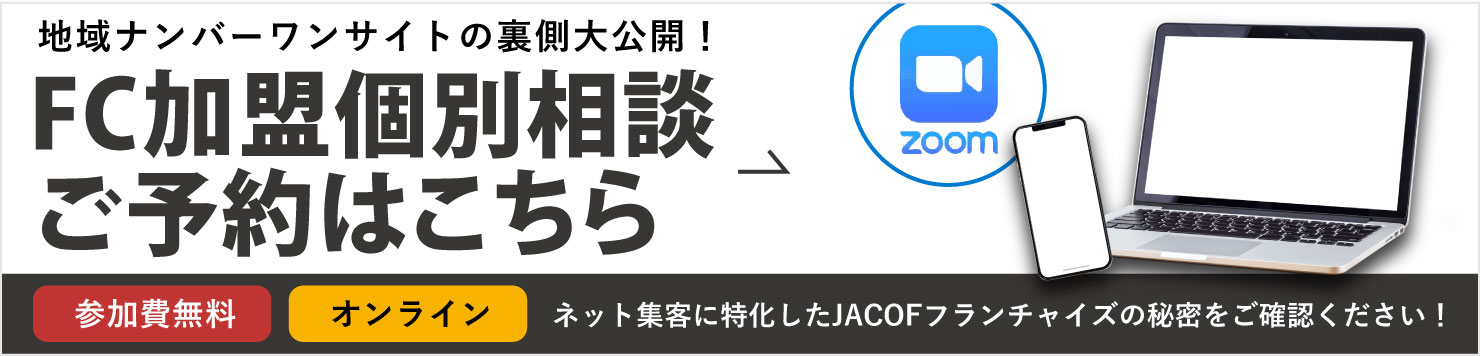「なぜあの会社は潰れたのか?」急増するリフォーム会社の倒産、その本当の理由と生き残る道
2025年6月30日更新
「黒字だったのに、なぜ潰れたんですか?」
利益も出ていた。職人もいた。依頼もそこそこ入っていた。
それでも――会社は静かに、そして突然、消えていきました。
なぜ今、リフォーム業界で倒産が急増しているのか。
どうすれば、この荒波を乗り越えられるのか?
このページが、あなたの“分岐点”になるかもしれません。
リフォーム会社の倒産が増えている理由とは?
「うちはまだ大丈夫」って思ってませんか?
――そのセリフ、倒産した会社の社長も、最後まで言ってました。
リフォーム会社の倒産が、いま止まりません。
2023年だけで82件。これは過去最悪のペースです。
このままだと、年間100件超えも現実になります。
資材は高い、仕事は減る、人は辞める。
まるで「三重苦の昭和ドラマ」。でも、これはフィクションじゃありません。
さて、あなたの会社はどうしますか?
倒産が多いのはどんなリフォーム会社?
倒産が相次いでいるリフォーム会社の多くは、小規模もしくは零細規模の事業者です。
実際、2023年1月から10月の建築リフォーム業における倒産82件のうち、負債額が1億円未満だった企業は約86.5%、従業員が10名未満だった企業は95.1%にも上ります。
また、「物価高」に関連する倒産では、資本金が1千万円未満の企業が7割以上を占めるなど、経営体力の弱い小規模企業が特に厳しい状況に置かれていることが浮き彫りになりました。
リフォーム会社が次々と倒れる“4つの現実”
倒産しているのは大手企業ばかりではありません。
中小企業を中心に倒産件数は急増。業界を取り巻く環境は、すでに“静かなる非常事態”に突入しています。
1. 価格は上がる、でも売値は据え置き――資材高騰の落とし穴
最も深刻なのが、建築資材の価格高騰です。
ウッドショックを皮切りに、木材や建材、さらには輸送費までが軒並み値上がり。2021年以降、資材価格は約30%も上昇しました。
仕入れるほど赤字になる。値上げをすれば「他社に乗り換えられる」
そう恐れて、泣く泣く利益を削る企業が後を絶ちません。
2. 市場が縮む中での消耗戦――「安ければいい」が業界を壊す
次に待ち受けるのは、受注の減少と激化する競争。
物価高が続く一方で、給与はなかなか上がらない。
そんな家計事情のなか、「いまはリフォームを見送ろう」と考えるご家庭が増えています。
この影響で、2024年のリフォーム市場は7.1兆円規模に縮小すると見られています。
限られた案件をめぐっての“価格勝負”が激しさを増し、採算度外視の受注も珍しくなくなってきました。
さらに深刻なのが、一部の不動産仲介会社が“リフォーム頼み”の収益モデルに傾いていること。
仲介手数料では利益が出ないため、リフォームで収支を合わせようと、価格を下げて案件を奪いにくる――。
この構図が、健全な競争環境を崩壊させつつあるのです。
3. 黒字でも倒産――「帳簿の数字」はウソをつく
驚くかもしれませんが、利益を出しているのに倒産する会社が増えています。
いわゆる「黒字倒産」です。
埼玉県のリフォーム会社「ユーワネクスト」は、売上こそ維持していたものの、利益率が極端に低く、資金繰りが限界に達したことで破産に追い込まれました。
帝国データバンクによると、建設業の価格転嫁率はわずか43.7%。
つまり、上がったコストの半分以上を、企業が自腹で吸収している状態なのです。
4. 人がいない。若者がいない。技術が続かない――人手不足の落とし穴
そして今、リフォーム業界を根本から揺るがす問題がもう一つ。
それが「職人不足」と「後継者不在」です。
建設業では約7割の企業が人手不足を実感しており、とくに技能職の高齢化と若手離れが深刻です。
このまま進めば、2040年には住宅建設の技能者数が約31万人も減少すると予測されています。
今後も“倒産ラッシュ”は続くのか?
残念ながら、リフォーム会社の倒産は今後もしばらく増え続けると見られています。
物価高の影響による倒産は、月に40〜50件のペースで続くと予測されています。
2025年、“働き手”が一気にいなくなる?
業界内では「2025年問題」が迫っています。
これは、団塊の世代――つまり70代のベテラン職人たちが、一斉に現場を離れていくタイミング。
経験豊富な職人が減れば、仕事は回らなくなります。
技術が引き継がれず、工事が遅れる。この流れは、今後ますます深刻になると見られています。
工事が進まない? 申請と追加費用の“壁”
さらに追い打ちをかけるのが、2025年4月からの法律改正です。
これまで不要だったリフォーム工事でも、「建築確認申請」が必要になるケースが増えるのです。
その結果
✔ 工事のスタートが遅れる
✔ 申請の手続きに手間がかかる
✔ 数十万円単位の追加費用が発生
現場にもお客様にも、重い負担となるのは間違いありません。
元請けで集客に悩む方には、ぜひおすすめしたいです。
そして今、大手が次々と市場に参入している
かつては地域密着の小さなリフォーム会社が中心だったこの業界。
しかし今、大手不動産会社やホームセンターが本格参入し、市場の様相が一変しつつあります。
広告力・資金力・ブランド力――
すべてを持つ大手と、個人事業や小規模事業者が同じ土俵で戦わなくてはならない時代がやってきたのです。
倒産を防ぎ、会社が続くために必要なこと
リフォーム会社がこれからも元気に続けていくには、新しいことにチャレンジしたり、経営のやり方を広げたりすることが大切です。
でも、やってみようとしても簡単ではありませんよね。
例えば、不動産の仕事だけをしている会社は、法律の決まりで「500万円以上の大きなリフォームはできない」など、できることに制限があります。
また、うまくいかない時の最後の手段として使われる「物件を買って売る仕事」も、銀行からのお金を借りにくくなったり、金利が高くなったりして難しくなっています。
倒産の多くは、実は「利益が出ていない」ことに気づくのが遅れた結果です。
だからこそ、現場ごとの費用と利益を、細かくチェックすることが重要です。
「この仕事は赤字になるかもしれない」
そんな案件を無理に引き受けていませんか?
また、取引先がきちんと支払いをしてくれるかを確認する「与信管理」も見直してみましょう。資材費や外注費の高騰が続く今こそ、お金の流れをしっかり見直すことが、会社を守るカギになります。
リフォーム業界の人手不足では、特に若い人たちが入ってこない。定着しない。そんな声をよく聞きます。
そこで必要になるのが、働きやすい環境づくりです。
☑仕事量に見合った給与体系
☑フレックスタイムや在宅ワークなどの柔軟な働き方
☑残業時間の見直しや無理のない勤務体制
こうした取り組みは、「人が集まり、人が辞めにくい会社」をつくるための土台になります。
人手が足りない今、頼りになるのが技術の力です。
たとえば――
・ARやVRを使った職人教育
・AIや自動化ツール(RPA)を使った事務作業の効率化
こうした取り組みは、「人に頼りすぎない会社づくり」に直結します。そしてなにより、少人数でも高い成果を出せる強いチームができていきます。
さらに、これらの導入には、国や自治体の補助金・助成金を活用することも可能です。
「うちは人もお金も足りないから無理」ではなく、“仕組み”で乗り越える時代です。
選ばれる会社になるには?
今、選ばれる会社には“共通点”があります。
逆に言えば、それがない会社はどれだけ真面目にやっていても、見向きもされなくなる時代です。
さて、その共通点とは?
☑“安心できる情報”がちゃんと伝わっている
たとえば、あなたが車を買おうとしているとします。車種だけ見せられて「いい車ですよ」って言われても、買う気になりますか?
・走行距離は?
・事故歴は?
・誰が点検したの?
・価格は妥当?
そう、人は「わからないもの」にはお金を出しません。
リフォームも同じです。
・ビフォー・アフターの写真
・価格の目安
・どんな人が来るのか
・お客様の声
こうした「安心できる材料」がそろって初めて「この会社にお願いしてみようかな」と思ってもらえるんです。
☑自分たちの強みを、自分たちが一番忘れてるかもしれない
長くやってると、自分たちにとって“当たり前”になっていることがあります。でもそれ、お客様から見たらめちゃくちゃ魅力かもしれません。
・自社施工だからできる柔軟な対応
・保証制度が手厚い
・地域での工事件数が多い
・ベテラン職人がずっと在籍してる
「それって他社も同じじゃないの?」
いえ、しっかり言葉にして伝えている会社は、意外と少ないんです。
顔写真を出す、資格を見せる、現場の空気感を伝える――。
たったそれだけで、お客様との距離はぐっと縮まります。
☑ネットで見つけてもらえなければ、“存在してない”のと同じ?
「うちは昔からのお客さんでやってるから」
「紹介がメインだからネットはいいや」
ほんの数年前までなら通用しました。でも、今は違います。
リフォームを考えている人の3人に1人は、まずスマホで検索します。
「〇〇市 リフォーム」「お風呂 交換 補助金」など、具体的なキーワードで探しています。
そこであなたの会社が出てこなければ、どれだけ実力があっても“知られていない”のと同じなんです。
WEB集客の重要性と成功事例
ある塗装会社は、SEO対策に力を入れてホームページを改善。結果、月10件以上の問い合わせと、売上が約4倍に。
何か劇的なことをやったわけではありません。
ただ、お客様が「知りたいこと」を、わかりやすく伝えただけです。
「選ばれる会社」になるとは、つまり
“見えない魅力”を、“見えるようにする”こと。
倒産するか、生き残るか――分かれ道は、情報発信にある
今のまま、ただ待っているだけでは厳しい。でも、伝え方を変えるだけで、結果はまったく変わってきます。
・どんな工事を
・いくらくらいで
・どんな人がやって
・どんな感想をもらっているのか
これを見える化すれば、お客様は「不安」ではなく「期待」を持って問い合わせをしてくれます。
「よし、やってみよう」
そう思った“今”が、動き出すタイミングです。